- HOME
- COURSES
- ACCESS
国内外で活躍している各界の社会人をお迎えし、自身の進路選択、仕事の内容、人生の転機や悩み、生き方をお話いただくオムニバス形式の授業です。多様な価値観や進路選択を知ることで、グローバル化や超高齢化、高度情報化などの変化にさらされる現代で柔軟に自らのキャリアを形成するための基礎、考え方を学びます。 ゲストスピーカーは企業、官公庁、大学・研究機関、国際機関などグローバルに活躍するトップリーダーから若手まで、多様な幅広い年代の方を予定しています。
すでに具体的に進路を定めている人はもちろん、「社会人ってキツくて大変そうだけど本当のところどうなのだろう」と仕事と生活について話を聞いてみたい人、「何をやりたいかわからないけれど進学選択の際に困らないようにとりあえず高い点数を取っておこう」と、考えるのを先延ばしにしている人も歓迎します。専門課程に進む前に自分の「これから」について考えてみましょう。

上西栄太
医療法人takk理事長
筑波大学医学専門学群卒業。名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科学修了(博士)。市中病院勤務後、大学院にてインスリン分泌機構についての基礎研究に従事。2018年より内科クリニックを開院。その後、小児・頭痛・呼吸器・疼痛・美容と専門領域の異なる分院を複数開院。「儲ける事は悪」という業界の空気感の中で、保険診療の持続性を高めるため「医療と医業の融合」をテーマに活動を続けている。開業後も精力的に研究活動を続けており、2024年には世界初の疾患報告も行っている。

河村真
楽天グループ株式会社 コマース&マーケティングカンパニーコマース&マーケティングテクノロジー統括部執行役員 ヴァイス・ディレクター
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)/

ハミルトン 純クレーグ
デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社 ライフサイエンス マネジャー
メルボルン大学Bachelor of ScienceにてGeneticsを専攻、東京大学大学院にて生物科学修士課程修了、博士課程単位取得退学。Genedata社のScientific Account Managerとして勤務後、2018年より有限責任監査法人トーマツに入職(現在、デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社と兼務)。デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社にて医薬品業界、及びライフサイエンス分野のパブリックセクターを対象にコンサルティングに従事。特に、バイオテクノロジー分野における事業戦略策定、バイオ領域のスタートアップエコシステム構築、創薬業界におけるデータやデジタル技術活用のテーマを中心に活動する。

末吉令美奈
株式会社アルマ取締役
京都大学大学院にて地域環境科学を専攻し、タイでのフィールドワークを通じて「仕組みづくり」の重要性を実感。その後、丸紅株式会社に入社し約17年間にわたり情報通信分野で事業開発・企画・M&Aに従事しました。国内外での豊富な経験(シンガポール・タイ駐在、通信事業会社への出向など)を通じ、デジタルサイネージ事業の立ち上げから、ASEANでの事業開発、ミャンマー通信民営化入札、海底ケーブルプロジェクトなど幅広い案件に携わりました。出産・育児とキャリアを両立しながら、時短勤務や育休を経て柔軟な働き方を実践。2024年以降は、両親が創業した株式会社アルマに参画し、会計を基盤とした経営支援を発展させる形で、フリーランス・エージェント事業「PRO WORKS」を立ち上げ、組織に縛られないプロ人材の活躍を支援しています。
本日は、株式会社アルマ取締役を務めておられる末吉令美奈様にご講演いただきました。
末吉様は京都大学農学部・大学院のご出身で、大学院時代はタイの山岳民族(カレン族)の村で、電気も水道もない中でのフィールドワークを経験されます。以前は、国連やJICAなどに代表される、発展途上国への支援を中心とした国際協力に関心を持たれていました。しかし、その活動を通じて「物質的な貧しさは必ずしも不幸とイコールではない」と知る一方、インフラや情報がないために不自由を被る現実を目の当たりにし、「国際協力」よりも「仕組み作り」がしたいと商社を志望されます。
卒業後は丸紅株式会社に入社。ご自身のバックグラウンドとは異なるIT部門に配属されますが、デジタルサイネージ事業の立ち上げやミャンマーでの通信事業入札、シンガポール駐在など、グローバルに活躍されました。しかし、ご長男が生後まもなく呼吸器疾患が見つかり、自力での呼吸も困難な中、NICUでの入院治療を行うという、ご経験をされ、ご自身の価値観が「仕事優先」から「子供優先」へと180度転換します。会社(丸紅)の理解あるサポートのもと時短勤務を続けますが、キャリアと子育ての両立に葛藤を感じる中で、「組織に依存しない働き方」の仕組みを作りたいという思いが強まります。
現在はご両親の会社である「株式会社アルマ」へ転職され、フリーランスの活躍を支援するプラットフォーム「PRO WORKS」といった事業の立ち上げなどを推進されています。「思い立ったが吉日」「気合いと根性」といった言葉に象徴されるように、ご自身の直感と価値観の変化に素直に従い、力強くキャリアを切り開いてこられた姿が非常に印象的でした。本日は貴重なお話をありがとうございました。
(工学系研究科化学システム工学専攻 苅谷航太)

須賀千鶴
経済産業省産業機械課長、製造産業DX政策企画調整官、AIロボティクス推進官(兼)デジタル庁参事官(現職)。
2003 年東京⼤学法学部卒、2009 年ペンシルベニア⼤学ウォートン校 MBA(医療経営専攻)。2003 年に経済産業省に⼊省。途上国⽀援、気候変動、クールジャパン戦略、霞が関の働き⽅改⾰、コーポレートガバナンス、FinTech、ベンチャー政策などを担当。2017 年「経産省次官・若⼿プロジェクト」にて「不安な個⼈、⽴ちすくむ国家」を発表。2018 年 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター初代センター⻑。

東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻 助教
横浜市出身。東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻 相関基礎科学系 博士課程修了。博士(学術)。専門は理論分子科学、分子非線形科学。数学とコンピューターを用いて、分子レベルの大きさの世界で起こるさまざまな興味深い現象の詳細を明らかにする研究を行っている。
.jpg)
松本美樹
阪急阪神ホールディングス株式会社
松本美樹氏
1993年阪急電鉄(株)入社。入社後、同社人事部へ配属以来、その後もグループ会社や事業本部において人事部門を中心にキャリアを歩む。自身の子育てとの両立経験をもとに、新規事業として駅チカの学童保育の立上げ・経営にもチャレンジ。現在は秘書部長として経営者の意思決定をサポート。
田邊 静夫氏
阪急阪神ホールデングス株式会社 グループ経営企画室 サステナビリティ推進部課長2003年東京大学法学部卒業後、阪急電鉄(株)入社。入社後、宝塚歌劇事業を経験し、現在はサステナビリティ経営を推進。

村松知明
㈱ミエタ 代表取締役
開成高校(2004年)・東京大学工学部(2008年)卒業。大学在学中に、卒業生と在校生が交流する大学公式プログラム「知の創造的摩擦プロジェクト」を創設し、運営代表者として2,000名規模に成長させた実績を持つ。新卒入社の三菱商事株式会社にて、8年間中国やフィリピンでの不動産事業等に従事。共に学業に励んだ学友たちの、社会に出て企業で思い描く活躍をすることの困難さや、また社会に対する自らのビジョンを行動に移せない現状を目の当たりにし、自分が受けてきた教育の中に大きな課題意識を覚える。自身の全てを注げる事業にコミットしたい、ゼロから変化を起こせる領域で起業したいという強い想いから、2016年に株式会社ミエタを創業。
本日は、東京大学をご卒業後、三菱商事株式会社での8年間の勤務を経て、現在は株式会社ミエタの代表取締役を務めておられる村松知明様にご自身のキャリアについてご講演いただきました。
村松さんは、ご自身の開成、東大、三菱商事という、いわば”エリートコース”を歩む中で、日本の「偏差値主義」に基づいたキャリアパスが本当にやりたいことを見失ってしまう現状につながっているのではないかという強い問題意識を抱かれました。そして、その課題を根本から解決すべく設立されたのが、現在の株式会社ミエタです。同社では、高校生などを対象に、社会課題をテーマにした「実践的な探究学習」を提供し、生徒が自らの興味や情熱を見つけ、社会と関わる機会を創出しておられます。
学生時代は偏差値競争を歩み、良い大学に行けば良い未来が待っているというように教えられてきた私にとって、村松さんのお話は自らのキャリアを深く見つめ直す良い機会となりました。特に、大学時代に「やりたいことがない」という焦りから、それまで打ち込んでいたテニスサークルを辞め、国内外の様々な活動に主体的に参加することで、最終的に心から没頭できるものを見つけられたご経験は、同様の悩みを抱える多くの学生にとって大きな転機を与えてくれるものであると感じました。「もし今日が人生最後の日なら、自分は何をするだろうか」というスティーブ・ジョブズの言葉を引用されながら、情熱を注げるものを見つけ、それをやり抜く「グリット」の重要性を熱く説く姿が非常に印象的でした。
本日は貴重なお話をありがとうございました。
(東京大学工学系研究科化学システム工学専攻 苅谷航太)

米澤かおり
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 母性看護学・助産学分野 講師
東京大学医学部健康科学・看護学科(現:健康総合科学科)で助産師・看護師・保健師の資格を取得、卒業。卒業後は助産師として東京北医療センター産婦人科病棟勤務。その後。東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻へ進学。博士(保健学)。大学院では副専攻として科学技術インタープリター養成プログラム修了。修士課程より一貫して新生児スキンケアに関する研究を行っている。

安丸芽生
2024年8月に東京大学教養学部教養学科国際日本研究コース(PEAK JEA)を卒業。 大学入学前の12年間をアメリカで過ごした経験から、日本における英語教育に関心を持ち、単身帰国。 「教育」一辺倒な大学4年間を過ごす中で、教育社会学との出会いや学校外教育に対する気づきを得る。 自身の関心分野である「教育」と「ことば」に携わることができると考え、2025年4月から出版社である株式会社Gakkenに入社
本日は、東京大学PEAKのご出身で、株式会社Gakkenに入社された安丸芽生さんにご登壇いただきました。現在は出版部出版販売課にて、資格書やムック・雑誌など幅広いジャンルの販売を担うほか、編集部と出版販売会社を繋ぐ役割なども務めていらっしゃいます。安丸さんは小学校1年時に米国移住後、英語を学ぶ中で、異なる言語に触れることが母国語への理解を深め、他者性を通じて世界の見え方を広げるという言語の働きそのものへ強い関心を抱かれます。また、父親の転勤により幼くして米国へ渡ったことで、本人の意思を超えて進路が方向づけられ、周りの同世代とは違う教育ルートの差が生まれたことに疑問を持たれ、教育に対しても強い関心を抱かれました。以上を踏まえ、大学入学以前は英語教員を目指されていたそうです。しかし、4年間の教職課程、加えて学部2年次に出会った「教育社会学」を通して、教育により得られた自身の立ち位置に対する違和感と向き合ったことで、別の選択肢を模索されます。その後の就職活動では、教育と言葉で何ができるかを考え、「本を通じて誰かの選択肢を増やす手伝いがしたい」との想いで、出版社を志望されました。入社後には、志望していた編集職ではなく営業職での配属ではあったものの「0→1を生み出すよりも、1→100に変える職業が自身の適正に合っている」という自己理解を武器に、幅広いジャンルを学び、市場全体を見渡す力を養っておられます。ご講演を通して、自身の境遇を外側から俯瞰できる点に安丸さんの強さを感じました。一般的な日本人では経験し得ない特殊な環境に身を置きながら、それを無自覚に当たり前とするのではなく、家庭事情や言語の壁といった自分では制御しにくい「運や社会構造」の点に捉え直すことは誰もができることではないと思います。安丸さん自身の努力も事実、運・構造の追い風も事実。その両方を認めた上で、自身の関心(教育や言葉)を「本」を介しながら「社会に還元する」姿勢に敬意を覚えました。この度はご講演ありがとうございました。
(総合文化研究科 広域科学専攻 小関大智)
キャリアサポート室
| 第1回 10月3日(金) | ガイダンス(オンライン) |
|---|---|
| 第2回 10月10日(金) | 村松 知明 氏 |
| 第3回 10月17日(金) | 安丸 芽生 氏 |
| 第4回 10月24日(金) | 須賀 千鶴 氏 |
| 第5回 10月31日(金) | 末吉 令美奈 氏 |
| 第6回 11月7日(金) | Coming Soon |
| 第7回 11月14日(金) | キャリアサポート室 |
| 第8回 11月28日(金) | Coming Soon |
| 第9回 12月5日(金) | Coming Soon |
| 第10回 12月12日(金) | Coming Soon |
| 第11回 12月19日(金) | Coming Soon |
| 第12回 12月26日(金) | Coming Soon |
| 第13回 1月9日(金) | 振り返りとまとめ |

磯貝友紀
ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社 チーフ・サステナビリティ・オフィサー
PwC Japan グループ Sustainability Center of Excellenceのリード・パートナーを経て参画。 2003年より、一貫してサステナビリティ・ビジネスに関与、「儲かるサステナビリティ」の推進に尽力。民間企業や世界銀行等で、東欧、東南アジア、アフリカ等の途上国におけるサステナビリティ・ビジネスを推進した経験を経て、2011年PwCのサステナビリティ部門に参画、日本企業CxO向けSX並走支援を多数実施。2022年より、SXによるトップライン向上を産業横断で検討するCEOフォーラム(Executive Sustainability Forum)を立ち上げ、活動をリード。 メルカリ「マーケットプレイスのあり方に関するアドバイザリーボード」有識者、 経産省J-startup推薦委員、金融庁「インパクト投資に関する勉強会」委員、ARCH 虎ノ門ヒルズイノベーションセンター メンター、一般社団法人科学技術と経済の会(JATES)専門委員会アドバイザー等を歴任。
10月18日の講義では、磯貝友紀さんにご講演いただきました。
世界の不平等解消やサステナビリティに貢献することを人生の軸にする磯貝さんですが,父とケーキを食べながら報道番組を見ていたら飢えた子供が映ったことに強い疑問を持ったこと、湾岸戦争を通じて大きな国際戦争を防ぐ仕事がしたいと思ったことが、原体験となったそうです。
貧困や戦争をなくす仕事に就くため国連就職を目指しますが、支援の本質を問いたいと高校生の磯貝さんは哲学科を志したそうです。しかしニューヨークの国連本部に電話で確認したところ文学部から国連には就職が難しいと言われたそうです。理系なら制限がないことや物理などが好きだった事もあり理科二類に入学されますが、哲学的な問いを解決せず国連に入り満足して仕事する事ができないという思いから三年で哲学科に進み修士まで卒業されました。そこで一定の納得感を得た上で国連就職を想定し、次は文化資源学の修士に進学されます。しかしその後、博士課程の進学がかなわなかったことや,移住先のオランダでの就職活動で苦戦した事が人生最大の挫折となったそうです。
ですが塞翁が馬。そのオランダではライフワークバランスと生産性向上は両立する事を体得されたそうです。次に住んだアフリカではサステナビリティビジネスは成立する実体験を得られたとお聞きしました。その後日本でPwCのサステナビリティチームに入り、日本でもライフワークバランスを取りながらビジネスを成立させる、社会や環境のためのビジネスを成長したいという思いが軸となりお仕事をしてきたそうです。
今年の8月にアフリカの時からの投資家になりたいという夢のためにJapan Activation Capitalに入社され現在に至ります。
質疑応答の中の「人々はミッションで繋がっており、ミッションが同じだと思った時に話を聞いてもらえる」という言葉を聞きました。また磯貝さんが仰っていた功利的にならずぶれない軸を持つことの大切さを強く感じました。そこに人生における幸せのヒントが詰まっているのかもしれません。
この度は素敵なご講演をいただき、誠にありがとうございました。
(総合文化研究科 広域科学専攻 佐藤満里奈)

岡村直樹
アステラス製薬株式会社 代表取締役社長CEO
1986年旧山之内製薬(株)に入社。以後、経営企画や事業開発に携わる。2010年に買収したOSI Pharmaceuticals社のCEOとして経営統合の陣頭指揮を執る。2012年にAstellas Pharma Europe Ltd.に出向し、欧州・中東・アフリカ事業の経営戦略担当SVPを務める。アステラス製薬帰任後は、事業開発部長、経営企画部長、経営戦略担当役員、代表取締役副社長経営戦略担当などの要職を歴任。2023年4月に代表取締役社長CEOに就任、現在に至る。
11月30日の講義では、アステラス製薬株式会社の代表取締役社長CEOとして活躍されている岡村直樹さんにご講演いただきました。岡村さんは、グローバル企業の経営者の視点で、そのダイナミックで挑戦に満ちた世界観を、学生時代から社会人での具体的なエピソードを交えながら紹介してくださいました。
高校時代、理数系科目が好きだった岡村さんは、黎明期にあったバイオテクノロジーの研究者を志して東京大学に進学されました。しかし、最初に受けた物理の授業で、教壇に集まる周囲の優秀な学生たちに圧倒され、学問への意欲を失う時期もあったようでした。薬学部へ進学した後も本業よりテニス活動に重きを置いていたことから、父親や教授から進路の助言があり、山之内製薬株式会社に入社することを決意されました。入社当初、岡村さんの学歴を見た人事部は、当然ながら研究・開発部門を志望していると考えていました。しかし、岡村さんご自身は「試験管から一番遠い部門で働きたい」と希望を出されました。周囲を驚かせても、自分の気持ちにしたがった数々の選択が、38年間にわたる製薬業界での活躍に繋がりました。
講演の中で岡村さんは、「CEOになるような人は失敗しないというイメージを持たれることがありますが、それは大きな誤解です」と語られました。実際、岡村さんは、会社の方針や決定事項に対して自分の意見を率直に伝えたことで、社内の摩擦も体験されました。それでも、当時の製薬会社の多くが国内市場を対象としている中、世界中で待っている患者さんのためにグローバル市場に目を向け、岡村さんは自ら行動し続けました。米国企業の買収や統合でも失敗を通じて学び、そうした経験を糧にして前進されてきたのです。
講演の中で特に印象深かったことは、岡村さんは、これからの10年、20年後を見据えた未来について、「その時代には課題も正解も予測できない、いわゆる『Unknown-Unknown』の世界が待っている」と述べられたことです。この不確実な時代を生き抜くためには、ひたすら目標に向かって突き進む「富士登山型」のキャリア形成だけではなく、その時々で見えてくるものに柔軟に従う「連峰縦走型」のキャリア形成も重要だと紹介されました。この考え方は、多くの聴講者の心に響き、質疑応答をより活発にしました。
(総合文化研究科超域文化科学専攻 小島広之)

岡本 佳子
神戸大学大学院国際文化学研究科講師
2014年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門分野は舞台芸術学で、オペラ作品の受容や古典化を研究中。在学中にブダペスト(ハンガリー)に政府奨学金給費生として留学。工学系学術団体での編集・国際担当職員を経て、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構特任助教、特任講師として教養教育開発に携わる。2020年から現職。家族は夫と子ども1人。神戸と東京を行ったり来たりして暮らしている。
本日は、このキャリア教室の初期の運営に携わり、現在は神戸大学大学院でハンガリーのオペラ・音楽劇を中心に研究されている、岡本佳子さんにご講演いただきました。会場には岡本さんのご家族もいらっしゃり、講演は時に賑やかに、明るい雰囲気で進行しました。
岡本さんが、ご自身のキャリアの中で大きな挫折の一つと位置づけたのが、博士課程修了後の進路でした。岡本さんはアカデミアでの就職活動がうまくいかず、一度民間の学術団体に就職し、フルタイムで勤務しつつ夜に論文を書く生活を送られました。結果的に様々な経験ができたものの、「このままここにいるのは違う」と感じ、再びアカデミアでの就職活動に踏み切ったそうです。このお話に関連し、会場の学生からは、「ある場所で『違うな』と思って別の場所に移動しても、そこでもまた『違うな』と感じてしまうのではないか」という、進路選択に際しての不安が寄せられました。これに対し岡本さんは、「『違うな』と思って様々な場所を転々とすることは悪いことではない」とした上で、「『ここじゃない』という現状打破の気持ちが変化のための強い原動力になる」と答えられました。
講演ではパートナーとの出会いや育児についても率直にお話しいただき、「ワークとライフは二項対立的に存在するのではなく、ワークはライフを構成する一つの要素であり、優先順位の問題」だと締めくくられました。また質疑応答では、パートナーの方も、留学や男性の育児に関する学生からの質問にお答えくださいました。お二人の実感がこもった言葉は、私を含め「進路を決断すること」に迷いや不安を抱える学生に対し、挑戦を励ますものになったと思います。この度はご講演いただき、誠にありがとうございました。
(超域文化科学専攻 齋藤海央)

小川 洋平
株式会社ゼンショーホールディングス 常務取締役
2004年に、東京大学教養学部を卒業、同年4月財務省へ入省。2016年に㈱ゼンショーホールディングスへ入社。以後、グループ全体の経営戦略に関わる。2018年にM&Aを行った北米を中心にテイクアウト寿司店を運営するAdvanced Fresh Concepts Corp.の取締役会長をはじめ、フェアトレード事業、海外外食事業の責任者などを幅広く歴任。2024年にグループのテイクアウト寿司の約1万店を統括するZensho International Limited 取締役会長に就任。
12月13日の講義では、株式会社ゼンショーホールディングスの常務取締役を務める小川洋平さんにご講演いただきました。小川さんは国際平和に関わる仕事がしたいという思いから学部をご卒業後、外務省での勤務を経て国際機関で働かれることを目指しておられました。しかしインド留学を通じてその国の人が自国の問題解決にあたる必要性を感じられて国内に目が向くようになったこと、そして官庁訪問の際に一緒に働きたいと思うような魅力的な方が多かったことから財務省に入られます。財務省ではボストンの大学への留学や二度の出向をはじめ12年間で12回以上の配置転換があり、ジェネラリストとしてのスキルを身に付けながらやりがいのある生活を送られていたそうです。しかしお父様が創業された株式会社ゼンショーホールディングスでのお仕事の魅力に惹かれ,転職をされたとのことです。
ゼンショーホールディングスでは、国・政府にできない取り組みを株式会社の力で実行し、社会に貢献できることが魅力とお話しされました。一例として、例えば能登半島地震の際は、会社のリソースを活かし,キッチンカーを用いて温かくて美味しい食事を届けられました。チャリティーではなく民間企業としての資源があったからできたことだとお話しされていました。
キャリア選択の際は、会社の大きさや給料で選ぶよりも、組織の理念に共感できるか、世の中にどのような貢献ができるか、成長産業なのかなども大切であるというお話を伺いました。またこれからは国際競争に勝ち残る必要がある時代だからこそのリーダーシップの重要性を強調されていたのが印象的でした。大企業の取締役の方からお話が聞ける貴重な機会の中から数多くの学びが得られた授業でした。この度はご講演ありがとうございました。
(総合文化研究科 広域科学専攻 佐藤満里奈)

沢登哲也
コネクテッドロボティクス株式会社 代表取締役/ファウンダー
東京大学工学部計数工学科卒業。京都大学大学院情報学研究科修了。新卒で飲食店の立ち上げと店舗再生に携わった後、MIT発ベンチャーでロボットコントローラ開発責任者を経て2011年に独立。産業用ロボットコントローラの受託開発を行い、2014年にコネクテッドロボティクス創業。2017年4月、飲食業に特化したロボットサービス事業を構想し、Startup Weekend Roboticsで優勝。以来「食産業をロボティクスで革新する」をミッションに食産業向けロボット事業に取り組む。
11月1日の講義では、コネクテッドロボティクス株式会社の代表取締役としてご活躍されている沢登哲也さんにご講演いただきました。沢登さんは、2017年から現在に至るまで「飲食」の領域でロボットサービス事業に取り組んでいらっしゃいます。ご講演では、現在の事業を起業するに至るまでの道程をありのままに教えていただきました。
大学院卒業後、沢登さんは、飲食店の立ち上げを目指して飲食業に従事し、1日あたり16時間にわたる立ち仕事の辛さや飲食業界に蔓延する人手不足を経験します。一度、飲食の世界から離れて大学・大学院時代に専攻した技術を活かす道を新たに探求し、2009年にMIT発ベンチャーでロボットコントローラ開発責任者として働き、2011年には独立、株式会社ポロックではロボットコントローラやアプリ、株式会社アステロではAI通知アプリを開発しますが、結果的にこれらの事業は失敗に終わってしまいました。しかし、かつての縁や私生活の充実などが逆風を跳ね除ける原動力となり、コネクテッドロボティクス株式会社の設立に至ります。
沢登さんが起業において重要だと考えるのは、流行りに乗るのではなく、「原体験や本当に好きなこと」に基づいたヴィジョンを持つことです。沢登さんにとっての「原体験や本当に好きなこと」とは、ご自身の祖父母が飲食店を経営していたこと、そして幼少期からロボットやゲームが好きで大学時代には作成にも携わったことでした。このことを踏まえて、今日では、食+ロボットを軸に事業を行っています。最近は「食産業をロボティクスで革新する」をミッションとして掲げて、私たちがスーパーで買うことができる惣菜などを作る食品工場向けのロボットを開発しています。
(総合文化研究科超域文化科学専攻 小島広之)

篠原量紗
文部科学省 高等教育局 私学部参事官付 経営支援企画室長
高校にて「社会は男女平等じゃない」と知り、大学にてジェンダーを学ぶ。性別によらないワークライフバランス探求がライフワーク。2022年夏より愛知&東京の2拠点生活に挑戦中。 2001年文部科学省入省。これまで初等中等教育、学術振興、人事、国立大学法人支援、産業連携推進を担当したほか、日本学術振興会サンフランシスコオフィス、東海国立大学機構名古屋大学にて勤務。 東京出身。お茶の水女子大学卒業。名古屋大学大学院修了。修士(教育)。
本日は、文部科学省で教育行政に広く携わってこられた篠原量紗さんにご講演いただきました。
篠原さんが仕事で重視されているのは「社会構造を変えることに貢献できているか?」という問いであり、それへの応答として、「性別によらないワークライフバランス探究」をライフワークに掲げられています。「社会は男女平等じゃない」という高校時代の気付きから出発したこの問いは、就職後のサンフランシスコでの経験や、家庭をもつに際しての発見など、様々な場面で再確認されたといいます。「公務員の中のマイノリティ」を自認され、必ずしも社会通念通りでないご自身の生き方・働き方が、1つの実例となること、それが認知されてゆくことの意義を強調されました。
講演内で紹介されたのが、「人はみなそれぞれのレンズを通して世の中を見ている」という考え方でした。これは個々人の価値観を相対化する発想であり、自分のレンズに自覚的になるだけでなく、他者の意見をその人固有のレンズとして捉え直すことが可能になります。その上で篠原さんは、様々な人と接し自分自身のレンズを増やすことで世界が広がり生活が豊かになる、大学ではできるだけレンズを増やすようにしてほしい、とおっしゃいました。
「仕事・ライフワーク・家族」は一体のものとされている篠原さんのご講演では、話題が多岐にわたっていながら、社会構造についての問いとライフワークが全体を貫く軸となっており、篠原さんご自身のレンズについて語っていただいたとも言えます。質疑応答の時間には、公務員の仕事についてだけでなく、“equality / equity”や当事者性の問題など、キャリアにこだわらない幅広い質問が寄せられました。
この度はご講演いただき、誠にありがとうございました。
(超域文化科学専攻 齋藤海央)

中島さち子
音楽家・数学研究者・STEAM 教育者
(株)steAm 代表取締役、(一社)steAm BAND代表理事、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー、内閣府STEM Girls Ambassador、東京大学大学院数理科学研究科特任研究員。国際数学オリンピック金メダリスト。音楽数学教育と共にアート&テクノロジーの研究も進める。
本日は、音楽、数学研究、STEAM教育など多方面にてご活躍されている中島さち子さんにご講演いただきました。
中島さんは、STEAM教育についてのお話の中で、ご自身の社会貢献の軸を「創造性の民主化」とされました。これは、それぞれの人の中に本来的に備わっている創造性を、できるだけ障害を取り除いて外に開いていくことだといいます。ここでいう創造性とは、奇抜な発明といった何か敷居の高いものではなく、学ぶことでうまれてくる躍動感や、異質なものを掛け合わせることによって生まれる新しさといった、もっと身近で幅広いものを包括しています。ご講演では、留学時の経験や国際的なセッションの場、万博に向けた準備など、これまでのご自身の経験の中にあった「おもしろかったこと」を生き生きと語られた上で、「とにかく動いてみれば何か得るものがある」、「自分なりにやること、自分のペースで自分の好きをつかむことが大切」と強調されました。学生からの「やってみておもしろくなかったことはあるか」という質問にも明快な言葉で答えられていて、それが成功であれ失敗であれ、自分自身の経験を自分なりに評価して価値付けすること、それ自体が一つの創造性なのではないかと感じました。
また、「多道、本質を観る、Sing your own Song!」や「論理と感性の狭間に人文知がある」など、中島さんのご講演では端的で目を惹く言葉がたびたび登場し、それぞれに中島さんご自身の経験に裏打ちされた定義がありました。質疑応答の際に受講生自身の興味や悩みが語られたように、シンプルな言葉だからこそ、受講生が自分に照らし合わせて考える機会にもなったのではないかと思います。
この度はご講演いただき、誠にありがとうございました。
(超域文化科学専攻 齋藤海央)

髙井賢太郎
弁護士
2002年東京大学法学部卒業。フリーター生活を経て慶應義塾大学大学院法務研究科を修了。2009年に検事任官し、全国各地の地方検察庁で刑事事件の捜査・公判業務に従事。その後、法務省刑事局にて刑事法の立案業務に携わったほか、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部に3年間出向し国連人権理事会等を担当。帰国後、法務省大臣官房国際課にて渉外業務を担い、2023年に弁護士登録。現在はスタートアップ企業の法務支援を中心に活動。
11月15日の講義では、2023年から代官山綜合法律事務所でスタートアップ企業の支援業務を中心に活動している弁護士の髙井賢太郎さんにご講演いただきました。
大学生時代の髙井さんは、やりたいことがいつかは見つかるだろうと考え 、さほど危機感をもたず就職活動もせずに卒業後はフリーターになられたそうです。その後、 様々な仕事を経験されたそうですが、勤務先での人員整理で生活が暗転する人たちを目の当たりにし、ご自身もいつ同じ目に遭うか分からないという不安感から生き方を変えようと一念発起して大学院で学び直し、法曹の世界に足を踏み入れ現在に至ります。
授業の中では数多の仕事を経験された髙井さんから多くのキャリアにおけるメッセージをいただきました。「どのような組織であっても、チャンスをつかむ のに大切なことは意外に単純であり、遅刻をせず、仕事の期限を守り、飲酒や異性関係でトラブルを抱えない人材であると評価されるだけでも、様々なチャンスがめぐってくる。 」という話は民間企業と官庁双方での勤務を経験された髙井さんだから話せる事だったのではないでしょうか。
私が最も印象に残った話は努力しているとチャンスは来る確率が上がるという話でした。「一生懸命やったからといって必ず評価されるとは限らない。しかし、一生懸命やることを続ければその様子を誰かが見てくれる確率は上がる。そして周囲は、一生懸命な人と認識した相手に仕事やチャンスを与えようとする。努力をするとチャンスが到来し易くなり、チャンスをものにするためには日ごろの努力が必要という関係がある。また、努力している人のもとには複数のルートから重層的にチャンスが舞い込む事が多い。」という話でした。授業を通じて努力することの大切さを改めて認識しました。
この度はユニークで楽しいご講演をありがとうございました。
(総合文化研究科 広域科学専攻 佐藤満里奈)

松倉茜
住友商事(株)、中東住友商事 財経部 経理課長
2004年に早稲田大学法学部を卒業、住友商事(株)に入社、主計部税務チームに配属。2007年2月〜2008年8月には米国住友商事(NY)にタックストレーニーとして赴任。その後は資源化学品事業部門やコーポレート部門の経理部署を歴任し、新規投資や事業会社管理、IFRS、消費税等、会計税務分野を担当。2022年6月より、中東住友商事(ドバイ)に赴任し、中東アフリカ地域の会計・税務の責任者を担っている。二児の母。趣味は着物。
10月11日の講義では、中東住友商事の財経部でご活躍されている松倉茜さんにご講演いただきました。現在、松倉さんはドバイを拠点に生活されており、今回の講義ではZoomを通してお話を伺いました。
早稲田大学法学部の学生だった松倉さんは、交換留学に応募するが一度は落選、しかし奮起し、英語の勉強やバイトに取り組みながら、在学中にカリフォルニア州立大学サンノゼ校に留学する機会を得ました。商社勤務の道を決めると、入社3年目にはニューヨークでトレーニーとして勉強し充実した生活を送りましたが、20代後半からはさらに高密度の生活を送ることになります。資源化学品部門の経理部で、オランダ、カザフスタン、ルーマニア、トルコなどに出張する等の激務を経験し、その後、結婚と出産を体験。妊娠→出産→復職というサイクルを2回経験し、コロナ禍の直前に復職。国際的な舞台でも家庭でも「がむしゃら」に活躍する中で、ドバイ勤務の話がやってきました。ドバイでは、家庭のことは夫が(在宅勤務をしつつ)中心に行い、松倉さんは朝に出勤し、夜に帰宅をする生活を送っています。この背景には「女性の働き方」の変化だけでなく、そのパートナーである「男性の働き方」が多様化している現実があります。価値観が多様な現代において、性にかかわらず「働き方」は柔軟に決まるといいます。学生たちには、何かを決めつけることなく、色々なことに取り組んでほしいと講演を結ばれました。
意外なことに、松倉さんは「何かをやりたい人は商社を選ばないほうが良い」と仰いました。「やりたいことが決まっているなら、それを専門とする会社に入るといい」。しかし、松倉さんのご講演では、ジェネラリストとして「半径3メートル」の身近な人たちを幸せにしながら、結果的に世界に貢献する「商社」での仕事の魅力がありありと伝わってきました。
(総合文化研究科超域文化科学専攻 小島広之)

兪程
コクヨ株式会社海外ファニチャー事業本部 事業戦略室
中国上海生まれ。復旦大学経済学部卒。2009~2010年東京大学教養学部短期交換留学(AIKOMプログラム)。2011年コクヨ株式会社入社。キャンパスノート発売40周年企画担当、期間限定体験型コンセプトショップ「コクヨハク」企画立案・実行責任者など文具事業のプロモーション活動を経験し、その後コーポレート広報にて、テレビCM・メディア発表会から社内報、統合報告書まで幅広くPR業務全般の経験に踏まえて、経営戦略推進メンバーとして海外家具事業のM&A後経営統合関連業務を携わる。その他、副業として、浅草にあるホテルTHE KANZASHI TOKYO ASAKUSAのリブランディング広報戦略立案およびイベント企画実行にも関与。
12月20日の講義では、コクヨ株式会社でご活躍されている兪程さんにご講演いただきました。
兪さんは大学3年生のとき、母校である復旦大学と東京大学との交換留学プログラムに参加し、1年間東京大学での学びを経験しました。その後、一旦中国に帰国し、卒業論文の執筆と並行して就職活動に取り組むという非常に多忙な日々を過ごされたそうです。
留学をきっかけに「日本で働きたい」という思いを抱くようになり、中国にいながらにして日系企業に焦点を絞って就職活動を進めましたが、多くの日系企業では外国人採用を現地採用に限定しており、日本で働くことが難しいという課題に直面されました。そのような中、少子化やデジタル・デバイスの普及により国内での文房具市場の縮小を予想していたコクヨが「アジア市場」に目を向けていたことを知りました。このような方針に魅力を感じて入社を決意されました。それ以後、兪さんは、文房具はもちろん、オフィス家具・空間設計やライフスタイルショップの運営も手がけるコクヨという舞台で、多岐にわたる分野で活躍されるとともに、社員の副業を応援するコクヨの方針に後押しされ、浅草にあるホテル「THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA」のリブランディングプロジェクトにも携わられました。
講演では、学生と社会人の違いとして「パラメーターの数」を挙げられました。進路がある程度決まっている学生とは異なり、社会人にはあらゆる局面で自己決定が求められます。そういった多様な要素の優先順位をつけることが、より良いキャリアの指針になることを強調されました。さらに、出産・育児に関連する体験についても語っていただきました。当初は出産後の帰国、翌年の職場復帰を予定していましたが、実際には帰国中にコロナ禍が発生。不安定な状況の中で幼い子供を保育園に預けることに不安を感じ、育児休業を延長されました。その間、会社の企業理念が変更され、広報職として理念を伝える役割を担う中で、大きなチャレンジに直面した経験も話されました。
最後に、「以不变应万变(不変をもって万変に応ずる)」という言葉を引用し、変化の多い環境の中で重要なのは揺るがない軸を持つことである、と締めくくられました。
(総合文化研究科超域文化科学専攻 小島広之)
キャリアサポート室
11/8の講義ではキャリアサポート室の方にお越しいただき、今後のキャリアを考えるきっかけや自分らしさを知ることを目的にワークショップ形式を主とした授業が行われました。3~4人のグループワークを中心とした授業で自己紹介の後、自分の人生をグラフにして振り返りグループのメンバーと共有することで自分らしさを見つけるワークや、社会人基礎力から自分の得手不得手を挙げながら特長を考えるグループワークを行いました。その上で社会人基礎力は経験で伸ばせることから、今後どのように能力をのばしていくかという開発計画を共有して授業は終了しました。
学生からの声としてはワークの中でグループのみんなにある共通点を発見できた、東大入学後の能力維持に対する心配を共有することで安心することができた、人生を通じてやりたいことが見つからない人が自分以外にもいて気が楽になったなどの声が上がりました。
また授業後レポートからは自分の人生を振り返る貴重な機会となった、グループのメンバーからの意見がとても参考になったという声や、将来などへの不安を共有する事で不安が和らいだという声もありました。これらの声を通じて、自分への理解が深まるだけでなく不安や悩みを共有できた事にもこの授業の意義があったのではないかと感じました。自分自身の事や今までの人生について、実は時間を取り客観的に振り返る機会は中々ないのではないでしょうか。私自身も大学1,2年生の時にこの授業を受講したかったと思いながら聞いていました。
キャリアサポート室の皆様、ありがとうございました。
(総合文化研究科 広域科学専攻 佐藤満里奈)
| 第1回 10月4日(金) | ガイダンス(オンライン) |
|---|---|
| 第2回 10月11日(金) | 松倉 茜 氏 |
| 第3回 10月18日(金) | 磯貝 友紀 氏 |
| 第4回 10月25日(金) | 岡本 佳子 氏 |
| 第5回 11月1日(金) | 沢登 哲也 氏 |
| 第6回 11月8日(金) | キャリアサポート室 |
| 第7回 11月15日(金) | 髙井 賢太郎 氏 |
| 第8回 11月29日(金) | 岡村 直樹 氏 |
| 第9回 12月6日(金) | 篠原 量紗 氏 |
| 第10回 12月13日(金) | 小川 洋平 氏 |
| 第11回 12月20日(金) | 兪 程 氏 |
| 第12回 12月27日(金) | 中島 さち子 氏 |
| 第13回 1月10日(金) | 振り返りとまとめ |

井原 徹 (いはらとおる)
日産自動車株式会社 専務執行役員, チーフHRオフィサー
1991年東京大学教育学部卒業、日産自動車(株)入社。入社以来、人事制度企画・改定、人財マネジメント、DEI、HRビジネスパートナー、ルノーとのアライアンス人事など日本国内での人事業務に加え、スペインや北米日産へ赴任し海外での人事など幅広く歴任。2019年1月同社理事(VP)、2020年4月同社常務執行役員(CVP)、2022年4月同社専務執行役員(SVP)に就任し、経営会議メンバーの一員としてグローバル人事戦略を担っている。
本日は井原徹さんにご講演いただきました。
井原さんは東京大学教育学部卒業後、日産自動車株式会社へ入社されました。入社以来、様々な人事業務を経験され、現在は専務執行役員としてグローバル人事戦略を担っておられます。今回の公演では、井原さんの学生時代から現在に至るまでの経歴をお話しいただきました。キャリアの中で特に目を引いたのは、海外経験の豊富さでした。学部3年生の時にアメリカに1カ月のホームステイ、入社3年目にスペイン、13年目にアメリカでの人事業務の赴任を経験されています。特にホームステイでは、ホストファミリーとの暮らしの中で文化の違いを肌で感じたそうです。この経験がダイバーシティに興味を持ったきっかけであり、現在の担当であるグローバル人事戦略へも繋がっているそうです。
また学生時代にやっていた方がよいことなどのアドバイスもいただきました。長年人事分野において活躍され、大企業の執行役員となられた井原さんのお言葉は説得力があり、とても視座が高いものでした。特に基礎学力と専門分野の知識をつけ、学ぶ力をつけるという部分は自身の研究活動と照らし合わせることが出来、自分の中に落とし込むことができました。将来的には固定的な専門性のみで戦っていくのは難しく、新たな領域に対してもそれを積極的に身に着けるといった学ぶ能力が重要になってくるとおっしゃっていました。この度はご講演いただき誠にありがとうございました。
(総合文化研究科 広域科学専攻 川原 功介)

カルソ 玲美 (かるそ れみ)
積水化学工業株式会社 コーポレート 新事業開発部 イノベーション推進グループ イノベーションカタリスト
学生時代から国際協力業界で活動を始め、国連やNPO、外務省、JICA(独立行政法人国際協力機構)でアフガニスタンやシリア難民支援、フィリピンでの新規事業立ち上げなどに携わる。2018年にはSDGs×データサイエンスのスタートアップ、サステナブル・ラボの創業期に参画し、組織・事業の立ち上げを経験。途中で産休・育休を挟みながら、CSO(Chief Sustainabilities Officer:最高サステナビリティ責任者)として人材、組織、社会のサステナビリティにコミット。2023年より、積水化学工業に移り、イノベーション推進の一環として、社内アクセラレータープログラムの運営、組織文化の変革・人材育成に携わる。
本日は、積水化学工業株式会社のコーポレート新事業開発部カルソ玲美さんにご講演頂きました。カルソさんは学生時代から国際協力業界で活動を始め、国連やNPO、外務省、JICA、フィリピンでの新規事業立ち上げなど多岐にわたる経歴をお持ちです。
カルソさんの講演の中心的なメッセージとして、「わがままに生きよう」という言葉がありました。経歴を見ると計画的・意欲的に行動されているように感じましたが、カルソさんの当時の内情や心境は、案外軽い気持ちだったり、失敗していたりすることがあったことをお話しされました。私は先のことを考えるのが苦手であり、将来への漠然とした不安を感じる日々でしたが、もう少し良い意味で適当に、気の赴くままに行動してみようと思うことが出来ました。
またカルソさんは、生まれる場所が異なるだけで人生における選択肢や機会が大きく異なる「格差」のことを、自らの経験に基づいて伝えてくださいました。日本社会で過ごしていると、正直「格差」はニュースやネットで見る単語であり、語られた実情は生々しく衝撃的でした。その上でカルソさんは、「私たちは恵まれているのだから絶対に失敗しない、恐れることなく好きなことをやってほしい」といったメッセージをお話しされました。私はこのメッセージが強く印象に残りました。「恵まれているのだから善いことをしよう」といった言葉はよく聞きますが、どこか絵空事と感じて消化しきれていませんでした。というのも後半の善いことが抽象的であり、自分の興味や好奇心とは距離のあるもので罪悪感を覚えるものだったからです。カルソさんのメッセージはその心のモヤモヤを晴らすもので、個人的にはより前向きに活動できそうな気分になれました。
社会に与えられた武器や、反対に無意識に縛られている部分をしっかりと受け止めつつ、自分の好きなことを目一杯できるような人生を歩みたいと思いました。
この度はご講演いただき、誠にありがとうございました。
(川原巧介 総合文化研究科広域科学専攻 修士課程1年)

龔 軼群 (きょう いぐん)
株式会社LIFULL ACTION FOR ALL / FRIENDLY DOOR 事業責任者 認定NPO法人Living In Peace 代表理事 一般社団法人Welcome Japan理事
上海生まれ東京育ち。中央大学総合政策学部卒業。2010年、株式会社LIFULLに新卒入社。不動産ポータルサイトLIFULL HOME’SではSDGs事業を立ち上げ、住宅弱者解決のための「FRIENDLY DOOR」の事業責任者を務める。 認定NPO法人Living In Peaceには2015年より参画し、マイクロファイナンスファンドの組成など担当。2018年、日本に逃れてきた難民の自立支援のためのプロジェクトを立ち上げ、代表理事に就任。また、難民・移民包摂の官民連携プラットフォームを担う一般社団法人Welcome Japan の理事も務める。
本日は龔 軼群さんにご講演いただきました。
龔さんのライフビジョンは「あらゆる人々に平等な機会を提供すること」であり、そのビジョンに向かって株式会社LIFULLにて住宅弱者解決のための「FRIENDLY DOOR」事業責任者を務める他にも、認定NPO法人Living In Peace 代表理事や一般社団法人Welcome Japan理事など、様々なアプローチで不平等問題に取り組まれています。
その背景には、龔さん自身が様々な不平等を感じて生きてきたということがあります。龔さんは上海生まれ、5歳より来日し育ったいわゆる移民二世です。今でこそ日本に日本国籍以外の人が住んでいることが普通と感じられる社会ですが、当時はまだまだ珍しいことだったそうで、それゆえ「私は、みんなとは違う」といった疎外感を感じる日々だったそうです。他にも留学や就活、従妹が来日したときの住居トラブルなど、中国籍であるが故の差別を受け、自分で選んだわけではないことによって不平等を被る社会に対して、激しい憤りを感じたそうです。そのような厳しい経験と怒りを原動力として社会で活躍されています。ただ自分が感じた不条理だけでなく、他人のそれも自分の中で社会への怒りへと変換し、全員にとって合理性のある社会を目指している考えがお話の節々に感じられました。他人のことでも自分事として取り組める感受性の豊かさようなものが、龔さんの最も秀でている能力のひとつであり、また自分も大切にしていきたい点だと思いました。また質疑応答の中で、「障害者の本当の気持ちを理解することは難しい、ただ不平等な結果が生まれているのでそこを解決する」と仰っており、他人の感情に鈍い私としてはとても印象に残りました。経験に基づく強い思いもって行動することや、障害者の気持ちを完全に共感することは出来ないにしても、社会をより良くする行いは誰にでも出来るのだなと感じました。
この度はご講演いただき誠にありがとうございました。
(総合文化研究科 広域科学専攻 川原 功介)

後藤 尚丈(ごとう たかひろ)
1996年、神奈川県出身。2015年に東京大学文科二類に入学。経済学部、経営学科に進学後、2019年に卒業。新卒で入社したグローバル系コンサルティング企業でサイバーセキュリティに係るキャリアをスタートした。2022年にデロイト トーマツ サイバー合同会社に入社し、サイバーセキュリティの領域におけるコンサルタントとしてのキャリアを開始。製造業、公共等様々な業種に対して、サイバーセキュリティの複数の領域においてプロジェクトに関与。
2011年東京大学経済学部経営学科卒業。在学中は「学生のためのビジネスコンテストKING運営委員会」に所属。新卒で水道工事業を手がける株式会社オアシスソリューションに入社。売上全国1位を取るなど営業職として4年間活躍後、人事部を立ち上げる。人事部在籍中、自社の制服リニューアルを担当したことがきっかけで、スーツに見える作業着「ワークウェアスーツ」を考案。2017年ワークウェアスーツ販売のため株式会社オアシススタイルウェアを立ち上げ、代表取締役に就任。2022年に退任し、かねてから課題意識を持っていた介護業界でフリーランスとして活動中。プライベートでは、社会課題の解決を通じて女子学生のリーダーシップと創造力を育むNPO法人ハナラボの理事を勤める。1児の母。
私が学部生の頃、国際関係に造詣が深いがIT関係にはあまり興味がなさそうな知人がしきりにサイバーセキュリティを話題にしていた時期があった。今から考えるとサイバーに関わる国際法(タリンマニュアル)の策定の時期だったのだろうと今になってわかる。
そのようなことを思い出しながら、本日の後藤尚丈氏の講演を聴講した。歴史や国際関係に興味を持ちつつ、高校時代より東大経済学部へ進学した自身の来歴を説き起こし、サイバーセキュリティという当時の新領域を「発見」するまでの経緯が語られた。元来の海外への興味など自身の選好が整理されたチャートは「自己分析」が機械的なものではなく、高度に知的な営みであることを認識させられた。後半のサイバーセキュリティコンサルタントとしてのお話では現在デロイトトーマツサイバー合同会社にお勤めの後藤さんの認識を活かして「経営のアジェンダ」となりつつあるサイバー部門の重要性が指摘された。コンサルタントとしての日々の生活や年功と専門性の関係など学生と年齢が近い方ならではの視点が多く、聴講する学生の多くにとって極めて実践的に役に立った方のではないだろうか。講演後の質疑でも志望動機などに関わるような具体的な質問が多かった。
今は既に過去である、というセリフがあるが、サイバーがハッカーたちの楽園だった世界も歴史となりつつある。先端領域がその領域を作った第一世代の手から「キャリア」として担う世代の手に移っていくとはどういうことなのか。ハッカーの組織化・集団化のような「余談」にクスリとしながらもそんなことを考えている。
(総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程 鈴木健吾)

木幡 浩
福島市長
1960年福島県生まれ。1984年3月東京大学経済学部卒業。 同年4月自治省(現 総務省)入省。岡山県副知事、消防大学校長、復興庁福島復興局長などを歴任。2017年に総務省を退職後、同年12月より福島市長。(現在2期目)。2023年から中核市市長会会長、東北市長会会長。 モットーは「開かれた市政」「スピードと実行」。物事をオープンにして市民共創を進めるとともに、地域経営の視点で、地域資源を最大限に活かし効果の最大化を模索。 福島復興は、復興を越えた新ステージづくりを進めることで達成できるとの考えのもと、度重なる逆境も成長のバネとして積極的市政を展開。「世界にエールをおくるまち」福島を目指している。
10月27日の講義では福島市長の木幡浩氏にご登壇いただきました。ご講演は福島県飯舘村ご出身の木幡氏の中での「3.11」の記憶から始まります。幼少時からのライフヒストリーの中で、学生時代の自由を満喫しながら、『キッシンジャー回顧録』などを読み公事に志した学生時代から「自由な職場」を目指されて旧自治省(現総務省)に入省されるまでのお話がありました。
長崎県と東京を往復しながらのキャリアは全編に渉り興味深いもので、殊に雲仙普賢岳噴火による防災政策変容の挿話はまとまった文章で読みたくなるような充実したものでした。また北海道大学公共政策大学院教授在任時のお話では、議員対象のサマーセミナーが開設された裏事情などにも話題が及びました。後段にキャリアは木幡氏の郷里・福島に向かっていきました。市長というポストが世の中を一番動かせる旨のご発言は自治体行政での豊富なご経験を表すものであると思いました。福島市長としての施策は災害対応から女性活躍まで多岐にわたっており、クリエイティブ産業従事者の誘致などは東京と福島の距離感なども考慮した効果的なものに感じました。受講者にも自身が首長になったつもりで物事を考える経験になったのではないでしょうか。質疑応答では自治体特有の仕事の進め方に関する質問や他自治体との差別化、就職の際の官民の選択など和気藹々としつつ緊張感のある質疑が展開されていました。
官僚たちの夏が遠く過ぎても公事に尽くされている姿は進路選択以前の学部学生のキャリア構想にも影響を与えたのではないかと思います。また、私自身は平成初年に生を享けた者として、折に触れて出てくる平成政治のワードに昨今話題の「平成ノスタルジア」を感じる場面もありました。この度は貴重なご講演どうもありがとうございました。
(総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程 鈴木健吾)

座間康(ざま やすし)
富士フイルム株式会社 取締役 執行役員 人事部長
富士フイルムへ1987年に入社。感材部業務課にて「写ルンです」 製品担当。大阪支社 販売第一部にてイオングループなど大手担当。1996年人事部へ異動し、 異動や採用、人材育成を担当。 2010年富士胶片(中国)投资有限公司 副総経理 兼 富士医疗器材(上海)有限公司 総経理。 2012年富士フイルム 人事部へ異動。2016年 人事部長。2019年 執行役員 人事部長。 2022年 富士フイルムホールディングス株式会社 執行役員 人事部長 兼 富士フイルム株式会社 取締役 執行役員 人事部長。 現在に至る。
本日は座間康(ざま・やすし)さん にご講演いただきました。座間さんはこれまで富士フイルム株式会社にお勤めで、現在は人事部門でご活躍されています。本講演では富士フイルム株式会社のこれまでの事業変革の原動力は「危機感である」という強いメッセージでとらえるところから出発し、座間さんのこれまでのエピソードをご紹介いただきながら、さまざまな業種・業界に進む可能性にある現代の受講者にも共通して必要な姿勢や意識についてご教授いただきました。さらに、これらにつながる「学生時代に準備できること」をご紹介いただき、参考にすべき重要な指針をお示しいただいたと感じています。これらは座間さんが人事部門において、ご自身も含めたさまざまな人の成長をはじめ「人」に関する多くのエピソードに接してきたからこそのメッセージであったと思います。現代社会の一員として期待される・求められる能力や価値というのはよく語られますが、往々にしてあいまいとしてつかみどころがありません。大組織においても、組織そのものはもちろん、そのメンバーも時代に応じて変化しなければならない、座間さんのお話の根幹にはそのようなはっきりとした人としての基礎力の大切さが感じられ、受講生にとっては学ぶことの多いご講演だったであろうと思います。この度はありがとうございました。
(院総合文化研究科広域科学専攻 修士2年 川下大響)

標葉 靖子(しねは せいこ)
実践女子大学 人間社会学部人間社会学科 准教授 兼 東京大学教養学部附属教養教育高度化機構客員准教授
大阪府出身。京都大学大学院生命科学研究科博士後期課程修了。博士(生命科学)。植物分子生物学・バイオインフォマティクス分野の研究で学位を取得後、帝人株式会社でナノエレクトロニクスやバイオ素材に関わる新事業開発・研究企画管理業務に従事。その後、東京工業大学環境・社会理工学院イノベーション科学系助教などを経て、2020 年4 月より現職。2023 年4 月からは東京大学教養学部附属教養教育高度化機構客員准教授も兼務。現在は主に科学技術イノベーションプロセスにおける分野・セクターを超えた多様な人々との「共創」のあり方について、科学技術社会論の立場から研究・実践を行なっている。 https://researchmap.jp/s _shineha/
本日は標葉靖子氏(以下、「靖子氏」)、標葉隆馬氏(以下、「隆馬氏」)にご講演をいただきました。現在靖子氏は実践女子大学に、隆馬氏は大阪大学にご所属であり、ご夫妻ともに研究者として活躍されています。
ご講演では、両氏のこれまでの出来事、ご関心を幼少の頃から順にたどり、現在のキャリア形成における重要な意思決定をどのよ な背景、意図でなさったかに注目してご説明いただきました。靖子氏は本キャリア教室の創設に携わっていらっしゃったとのことであり、これはまさに「キャリア教室」の誕生をたどるものでもあったと感じています。
研究者としてのキャリアも、靖子氏は博士修了後の最初のキャリアに民間を選び、のちに大学に転職された一方、隆馬氏はいわゆるアカデミア一本のキャリアを経られるなど両氏で大きく異なり、特に研究者を志す受講者にとってはその進路の見通しについてよく参考になったでしょう。 さらに、女性側の視点に偏りがちなライフイベント・ワークライフバランスにかかる問題については両氏の視点からの言及があったことのみならず、特にいわゆるテニュア(無期雇用)の取得までは地域を跨いだ異動も多い研究者という職業上の特性もあり大変貴重なものでした。
大学にいる身分にも関わらず、研究者・大学教員のキャリア形成について聞く機会は必ずしも多くありません。その中で、今回のご講演はすでに将来の職業に研究者を考える受講者にとってはもちろんのこと、自身の将来に問題意識を持つすべての受講者にとって得るものが多かったのではないかと思います。ありがとうございました。
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 川下大響
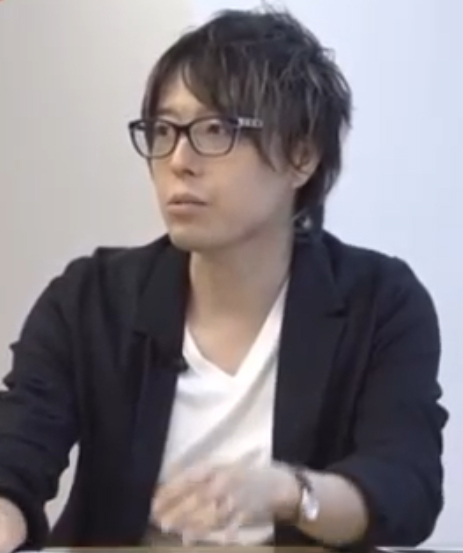
標葉 隆馬(しねは りゅうま)
大阪大学 社会技術共創研究センター 准教授
宮城県出身。京都大学農学部応用生命科学科卒業。同大学大学院生命科学研究科博士後期課程修了。博士(生命科学)。総合研究大学院大学・助教、成城大学・准教授を経て、2020 年4 月より現職。専門は科学社会学・科学技術政策論。先端科学技術の倫理的・法的・社会的課題 (ELSI) の可視化、定量メディア分析、コミュニケーションデザイン、政策分析などを組み合わせながら、複数のプロジェクトの代表者として幅広く研究・実践中。 主著に『責任ある科学技術ガバナンス概論』(ナカニシヤ出版 2020) ほか、論文多数。日本学術会議連携会員、若手アカデミーメンバー、他なんか色々。
本日は標葉靖子氏(以下、「靖子氏」)、標葉隆馬氏(以下、「隆馬氏」)にご講演をいただきました。現在靖子氏は実践女子大学に、隆馬氏は大阪大学にご所属であり、ご夫妻ともに研究者として活躍されています。
ご講演では、両氏のこれまでの出来事、ご関心を幼少の頃から順にたどり、現在のキャリア形成における重要な意思決定をどのよ な背景、意図でなさったかに注目してご説明いただきました。靖子氏は本キャリア教室の創設に携わっていらっしゃったとのことであり、これはまさに「キャリア教室」の誕生をたどるものでもあったと感じています。
研究者としてのキャリアも、靖子氏は博士修了後の最初のキャリアに民間を選び、のちに大学に転職された一方、隆馬氏はいわゆるアカデミア一本のキャリアを経られるなど両氏で大きく異なり、特に研究者を志す受講者にとってはその進路の見通しについてよく参考になったでしょう。 さらに、女性側の視点に偏りがちなライフイベント・ワークライフバランスにかかる問題については両氏の視点からの言及があったことのみならず、特にいわゆるテニュア(無期雇用)の取得までは地域を跨いだ異動も多い研究者という職業上の特性もあり大変貴重なものでした。
大学にいる身分にも関わらず、研究者・大学教員のキャリア形成について聞く機会は必ずしも多くありません。その中で、今回のご講演はすでに将来の職業に研究者を考える受講者にとってはもちろんのこと、自身の将来に問題意識を持つすべての受講者にとって得るものが多かったのではないかと思います。ありがとうございました。
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 川下大響
関根 澄人(せきねすみひと)
株式会社博報堂 ミライの事業室 ビジネスデザインディレクター 兼 Earthhacks株式会社 代表取締役社長 CEO
東京工業大学大学院生命理工学研究科修了。 学生時代、細胞学を研究しながら、生物多様性や地球温暖化など環境問題を伝えていくことを仕事にしたいと思い、博報堂に入社。入社後はビジネスプロデュース職として様々な企業のブランディングなどを担当し、博報堂従業員組合の中央執行委員長を経て、2020年よりミライの事業室ビジネスデザインディレクター。 2020年4月から3年間三井物産に出向し、2023年に博報堂と三井物産の合弁会社としてEarthhacks株式会社を設立。
第10回のキャリア教室では、日本の広告業界をけん引している株式会社博報堂と、博報堂・三井物産の合弁会社であるEarth hacks株式会社の両社でご活躍されている関根澄人さんにご講演いただきました。学生時代はM-1グランプリにも出場されたことがあるというお笑い好きな一面もある、関根さんのパワフルで面白い語り口に学生一同引き込まれました。また「日常でできる身近な環境問題解決」をテーマにクリエイティブな活動をされていらっしゃる関根さんは、理系文系にこだわらず“やりたいことをやる”クリエイティブなキャリアを提示してくださいました。
“やりたいことをやる”ための「向き不向きより前向き」「エトス→(信頼)→パトス(情熱)→ロゴス(論理)」という2つのキーワードを伝えていただき、関根さんの周りを動かす力の源もここにあるように感じました。取りたい案件のために何度も挨拶に行く、などエネルギーあふれるお話にとても驚きました。その実行力のおかげで、人との関係性で最も重要な“エトス=信頼”を得ている関根さんの周囲から信頼され親しまれているお人柄が伝わってくるエピソードでした。人の信頼を得るのは簡単ではありませんが、受け手が誰で何を欲しがっているかを考え、「発言+行動」していくことがとても重要だと感じました。関根さんのお話を聞き、失敗しても誰も気にしないのでどんどん挑戦しようという前向きな気持ちになりました。
また、アイディアを沢山思いつくにはどうしたらいいかという質問に対し、とにかく生み出していくことが重要で、クリエイティブの原点とは「みんなが気付いているが素通りするような些細なことを言葉にして相手に伝える」ことだと仰っていたのが印象に残っています。
貴重なお話ありがとうございました。
(総合文化研究科広域科学専攻修士課程一年 中井香里)

Austin ZENG
MEXT Scholars Association創立者・理事 兼 ITベンチャー・エンジニア 兼 フリーランスWeb開発者、翻訳通訳
第六回のキャリア教室には、本学の卒業生でもいらっしゃるAustin ZENGさんにご講演いただきました。Austin さんはシンガポールご出身で、学部から日本に留学され、現在はフリーランスで翻訳・通訳、エンジニア、留学生支援など幅広い分野でご活躍されています。
今回の講演では、Austin さんの多岐に渡るキャリアと学生のキャリア選択についてお話しして頂きました。「21世紀のキャリアは迷っていい」と仰っていた通り、コロナ禍で通訳のお仕事が激減する一方、プログラミングのお仕事をされていたので結果的にリスクが分散された例を挙げられ、一つのことを極める“スペシャリスト”にならなくても複数分野に跨がる“ジェネラリスト”になるのも良いという選択肢を提示してくださいました。
また、日本における留学生の就職の難しさについての問題意識から留学生支援の団体を設立された際のお話しを伺った際には、団体設立から価値提供、自身のポジショニングといった、これからの社会を渡っていくための“組み合わせ技”をレクチャーして頂きました。
活動分野が多岐に渡られているAustin さんですが、“人脈”と“フッ軽さ”が大事だと仰っており、Austin さんの魅力的な人柄からもそれが伺えました。機会を掴むためにそれを掴める状態に自分を置き、とてもエネルギッシュにご活躍されているAustin さんの軸となっているのだなと感じました。
「提供できる価値の希少性✖️数」を踏まえて自分のブランディングをするというお話は、試行錯誤真っ只中の学部生にまさに響くものだったと思います。私も興味があることにはフットワーク軽く挑戦していきたいと思います。この度は貴重なご講演どうもありがとう
ございました。
(総合文化研究科広域科学専攻修士課程一年 中井香里)

野口 晃菜 (のぐちあきな)
小学校6年生の時にアメリカへ渡り、障害児教育に関心を持つ。高校卒業後に日本へ帰国、筑波大学にて多様な子どもが共に学ぶインクルーシブ教育について研究。小学校講師、企業の研究所長を経て、現在一般社団法人UNIVA理事として、学校、教育委員会、企業などと共にインクルージョンの実現を目指す。文部科学省「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」など。共著に「差別のない社会をつくるインクルーシブ教育」など。
第一回のキャリア教室には、「インクルーシブな社会」の実現を目指し活動されている野口晃菜さんに来ていただきました。
野口さんは小学六年生から高校生までをアメリカで過ごされ、筑波大学にご入学し、同大学大学院で修士課程を修了後、小学校特別支援教育支援員を経て、博士号取得と平行しながら (株)LITALICOで発達障害のある子ども達への支援・教育の促進活動に携わられました。現在では一般社団法人UNIVAの理事として学校・企業・少年院といった場でのインクルーシブ教育の促進に取り組んでおられます。また、今年一月にご出産されたばかりで講義に娘さんもご一緒にいらっしゃり、教室みんなで見守る瞬間もありました。
野口さんは、学生時代にアメリカで障がい児と同じ教室で授業を受けたことをきっかけに多様性やマイノリティ差別などに興味を持たれ、「障がいのある人もない人も過ごしやすい社会を作りたい」というビジョンのもと一貫して活動なされています。会社の役員として障がい児の教育支援に取り組んでいた時は、10年間ほぼ休みなく働いていたとおっしゃられていたのですが、お話を伺っているだけでも野口さんのパワフルなエネルギーが伝わってきました。
今回の講義では、キャリア選択が一番学生が悩むポイントだったように思います。野口さんが「自分のビジョンに向かって、自分のやりたいこと・自分ができることをとにかくやってきた」と語っていらしたところが印象に残っています。やりたいことがまだ分からないという質問に対しては、「アンテナを張って自分の心が動いたところを見つける」ともアドバイス頂きました。今まさに将来を考え初めている学生にとってとても貴重なお話を聞かせていただき、大変ありがとうございました。
中井香里 (総合文化研究科 修士課程)

吉原 優子(よしはらゆうこ)
循環畑 実践観察家 Natural Organizations Lab(株)共同創業者
京都大学法学部卒業。2006年関西電力入社。長期成長戦略策定に携わる。2011年オーダー靴の靴職人として修業を開始し、2013年に「ユメノハキゴコチ」を開業。「オシャレ×履き心地が良い」ハイヒールを探究し製作する。靴づくりで土に還らないゴミが出ていくのを目の当たりにし、自然の循環とは何かを考え始めた時、自然農法・無肥料栽培に出会い、様々な先駆者から学ぶ。2017年Natural Organizations Lab株式会社設立。循環を活かした畑を作ることができる方法を日々実践研究中。『循環畑から感じる ティール組織』執筆中(日本能率協会より来春出版予定(吉原史郎と共著))
研究においても趣味の読書においても功成り名を遂げた人物の回顧録を読むことについて一般に難しいのは、その「キャリア」が予定調和的に構築されたように見えてしまうことである。「私は最初からわかっていました」式の回顧録に筆者も(研究上)悩まされているが、予定調和ではないキャリアの物語として、12月1日の吉原優子氏のご講演は素晴らしいものであった。
京都大学法学部で学生生活を送り、法曹志望から転換した吉原氏は関西電力に入学する、ものつくりに志し、靴作り職人に弟子入りする。企業つとめの時間を修行に活用するために靴職人専業になった吉原氏はブランド「ユメノハキゴコチ」の立ち上げに成功する。メディアの取材などを含めた前半は個人事業の立ち上げ方という面で非常にアクチュアリティがあった。
後半は靴の製作時のゴミへの気づきもあり、「無肥料栽培」の岡本よりたか氏との交流もあって、「循環畑」を生み出し、あらゆる人が参画できるような農業を試みていく。ティール組織など経営学の知識などを交差させつつ、栽培植物の野生に近い姿を示すなどの工夫は実験型の授業のようでもあり、農業の知識がなくても楽しめるものだった。イギリスでのお話もあったが、海外での農業経営などのあり方など、お聞きする機会があればと思う。
学歴に”見合う職業”という自縄自縛(これは受講者との質疑であったものである)を振りほどき、内発的な動機を大切にされた姿は博論段階で超域的な研究に身を投じてしまった自身にも励みとなった。ご講演内の言のように、「ヘルシーな」研究生活につとめていきたいと思う。
(総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程 鈴木健吾)
キャリアサポートー室 ワークショップ
今回は本学キャリアサポート室のスタッフの方々にお越しいただき、学生自身が主役としたワークショップ形式の授業を行いました。このワークショップの目的は、「自分らしさ」とは何かを知ることです。変化が激しく、不確かな未来の中で、「自分らしさ」を中心に人生を創り上げていくことが重要であると考えられます。
最初に「自分らしさ」を見つけるためのワークを行いました。これまでの人生をライフラインチャートで表し、過去の経験を振り返ることで自分の特徴を探りました。またそれをグループで共有することで、他の人の視点も含めた自己理解が深められました。各人全く異なった特徴が浮き彫りとなり、これまでの自分たちにも多彩な人生があることが小人数のグループワークでも理解することができました。また他者との会話を通じて、新たな「自分らしさ」の発見があった生徒もいたようです。
次に自分が持っている「社会人基礎力」(職場や地域社会で多様な人々と仕事をするために必要な基礎的な力)について考え、今後伸ばしていきたい能力の選択とその手順を考えました。「社会人基礎力」は社会人としての基盤能力であり、経験を通じて後天的かつ意図的に身につけられる力です。得意な力をより伸ばそうとする学生や、苦手な力を補強する学生など、様々な方針が立てられました。
今までの授業では招待講師が主体となっていましたが、今回の授業は学生自身が主体となり、より自分と向き合える授業であったと思います。今までの授業で思ったこと、感じたことを、自分の人生と照らし合わせる機会にもなっていたのではないでしょうか。
(総合文化研究科 広域科学専攻 修士課程1年 川原 巧介)
| 第1回 10月6日(金) | ガイダンス(オンライン) |
|---|---|
| 第2回 10月13日(金) | 野口 晃菜 氏 |
| 第3回 10月20日(金) | カルソ玲美 氏 |
| 第4回 10月27日(金) | 木幡 浩 氏 |
| 第5回 11月10日(金) | 龔 軼群 氏 |
| 第6回 11月17日(金) | Austin ZENG 氏 |
| 第7回 11月21日(火) | 標葉 靖子・標葉 隆馬 氏 |
| 第8回 12月1日(金) | 吉原 優子 氏 |
| 第9回 12月8日(金) | 井原 徹 氏 |
| 第10回 12月15日(金) | 関根 澄人 氏 |
| 第11回 12月22日(金) | 座間 康 氏 |
| 第12回 1月5日(金) | 後藤 尚丈 氏 |
| 第13回 1月19日(金) | キャリア・ワークショップ/ふりかえり |

小見 和也
H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 研究開発担当 合同会社H.U.グループ中央研究所 社長 富士レビオ株式会社 取締役、株式会社エスアールエル 取締役 など
1979年新潟県出身. 東京大学文科3類入学, 医学部健康科学・看護学科卒業.同大学院医学系研究科博士課程を修了後(保健学博士), 検査薬・製薬企業にて検査・医薬品の研究開発, 大学・ベンチャー企業との共同研究開発, M&Aなどを担当.ヘルスケア領域で新技術/製品の発案・発明, 製品化・事業化などを主導するとともに、技術系人材育成・イノベーション型組織の設計・運営に携わっている.
年内最後となる今回の授業では、”技術系経営者”として活躍される小見和也様にご講演いただきました。小見さんは本学文科III類に入学し、大学院医学系研究科博士課程を修了後(保健学博士)、検査・医薬品の研究開発, 大学・ベンチャー企業との共同研究開発, M&Aなどを担当されたご経験があります。また、新技術/製品の発案・発明, 製品化・事業化などを主導するとともに、技術系人材育成やイノベーション型組織の設計・運営にも携わっておられます。
講義では、ご自身のご経歴と、現在のお仕事内容についてご説明された後、未来の予測が難しく、日本企業の衰退が見られる中で、二十年後を担う学生たちにメッセージをくださいました。一つ目は、自分の人生を生きる、つまり、自分にとっての「幸せ」の定義を早く見つけるということ。二つ目は、好きなこと・夢中になれることを通じて一万分の一の人材になる(稀少性を獲得するということ、人に勝っているという軸から人と違うという軸へ)。そして、三つ目は、イノベーションを起こすということです。
「自分自身が様々な経験をしてきて、そこで得たものを次の世代に共有していきたい」と話す小見さんによる照然たるメッセージが学生にとって大きな刺激、励みになったと思います。
松本 岳(東京大学大学院総合文化研究科 修士課程)

高祖 歩美
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)広報室長。
東京大学を卒業後、首都大学東京大学院で博士号を取得。ライフサイエンス統合データベースセンター、科学技術振興機構、東京大学、人間文化研究機構において広報職に携わり、現職。2018年に日本における科学コミュニケーションの英語コミュニティ、ジャパン・サイコム・フォーラム(Japan SciCom Forum)を共同で立ち上げ、運営にあたるほか、科学報道をテーマとした調査研究を行っている。
本日は、複数の研究機関で広報担当として活躍されてきた高祖歩美さんにご講演いただきました。
高祖さんは、英国で高校を卒業し、本学を卒業後、首都大学東京大学院で博士号を取得されました。その後は本学や人間文化研究機構などで研究成果に関する広報職に携わり、現在は国立遺伝学研究所で同研究所を中心としたナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)の広報をされています。本講演では、学生時代の話や広報の業務についてだけでなく、育児や家庭についてもお話しいただきました。
ご講演では、まずご自身の学生時代についてお話しされました。研究室に配属された際の葛藤と大学院へ進む際のエピソードなどについて話されました。その後は、大学や研究機関の広報の業務についてお話しくださり、特にノーベル賞授賞式の内幕や、江戸の料理書に関する研究成果のアウトリーチ活動といった具体的な業務についての話には、多くの学生が興味深く聞いていました。また、育児の話では、「子供の成長に負けないように自分も日々成長したい」との言葉に勇気づけられる学生がいたようです。また、授業終了後、学生からは具体的な質問が多く寄せられ、関心の高さが伺えました。高祖さん曰く、広報とは、人々の意識や行動の変化を促すことを目的とした活動であり、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかが重要な要素になるそうです。研究機関の広報は、研究と社会をつなぐためのものであり、その重要性は計り知れません。広報という仕事について、そして、その実践について考えることは、学生にとって有意義な時間になったと思います。この度はご講演いただき、ありがとうございました。
(松本岳 総合文化研究科 修士課程)
写真.jpg)
佐野 悠樹
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付
1992年生まれ。桐朋高校(都内)を卒業後、理科2類に入学。学部ではオーケストラサークルに所属。農学部に進学後、農学生命科学研究科修士課程を修了。副専攻として「科学技術インタープリター養成プログラム」も受講。2017年、農林水産省入省。農林水産省では、農林水産研究行政や農業資材(農業機械、肥料など)行政等を担当。現在、内閣官房で国家の危機管理を担当。趣味は楽器演奏(ファゴット、バイオリン)、テニス、ボードゲーム。
本日は内閣官房にお勤めの佐野悠樹さんにご講演いただきました。
佐野さんは大変気さくな方であり、また今年度の登壇者の中では最もお若く学生とも年代が近いという事実も相まって、参加者全員がとてもリラックスした様子の授業で率直なお話を多くお聞きすることができました。
佐野さんは農学生命科学研究科修士課程を修了した後、2017年に農林水産省に入省されました。修士課程においては植物の遺伝子解析の研究をされており、農林水産省では、農林水産研究行政や農業機械、肥料などの農業資材行政等を担当されていたということです。
そして昨年、内閣官房へ出向し、現在まで1年半ほど、危機管理に関する部署で働いているということでした。
佐野さんの内閣官房での業務は農林水産省の業務とは異なる点も多かったそうで、業務にあたってはマニュアル・本で勉強をすることも多いとの事でした。また、担当業務の性質上、緊急対応が必要な場合には昼夜を問わず直ちに駆けつける必要があるとおっしゃっており、講義当日もまさに未明に対応を求められていたというお話があった際には、学生のうちに驚きと感嘆の表情が見られました。
“仲が良い”という定松先生からは「自由人」との紹介があったように、特定の事や物に固執する事なく、急な異動にもフレキシブルに対応することができる方だという印象を受けました。
今まさに官僚としてキャリアを積まれている方の”生の声”を聞けたという点は私にとっても大変貴重な経験となりました。
この度はご講演いただき、誠にありがとうございました。
仲川久礼亜(総合文化研究科 博士課程)

中村 有沙
フリーランス 株式会社オアシススタイルウェア 前・代表取締役 NPO法人ハナラボ理事
2011年東京大学経済学部経営学科卒業。在学中は「学生のためのビジネスコンテストKING運営委員会」に所属。新卒で水道工事業を手がける株式会社オアシスソリューションに入社。売上全国1位を取るなど営業職として4年間活躍後、人事部を立ち上げる。人事部在籍中、自社の制服リニューアルを担当したことがきっかけで、スーツに見える作業着「ワークウェアスーツ」を考案。2017年ワークウェアスーツ販売のため株式会社オアシススタイルウェアを立ち上げ、代表取締役に就任。2022年に退任し、かねてから課題意識を持っていた介護業界でフリーランスとして活動中。プライベートでは、社会課題の解決を通じて女子学生のリーダーシップと創造力を育むNPO法人ハナラボの理事を勤める。1児の母。
本日は現在介護業界においてフリーランスでお仕事をされている中村有沙さんにご講演いただきました。
中村さんは経済学部経営学科卒業後、水道工事業を手がける株式会社オアシスソリューションに入社されました。営業職として4年間活躍後、自社への問題意識から人事部を自ら提案し立ち上げを行われました。人事部在籍中には、スーツに見える作業着「ワークウェアスーツ」の考案が功を奏し、2017年にはワークウェアスーツ販売のため株式会社オアシススタイルウェアを立ち上げ、代表取締役に就任されました。そして本年からは、心機一転、介護業界にてフリーランスでご活躍されています。
中村さんの華々しいキャリアと明るく快活に話される姿を見ると、迷いなくキャリア選択をされてきたように見受けてしまいますが、講演の中では、実際は何度も進路に迷い挫折も経験し、自身の引っ込み思案な性格とも愚直に向き合った結果、現在があるということをお話くださいました。
人生・仕事における選択に際してどのようなことを思いどのような点を重視したか、具体的にどのようなアクションが功を奏したかということをかみ砕いてお話しくださり、我々にとって大変励みになるだけでなく、一人一人が自身と向き合う上で活かせる知恵を多くご教授いただきました。
中村さん自身が最後におっしゃった3つのメッセージ、
やりたいことは試しに先取りしてやってみること。
困った時には尻込みせず人に教えてもらうこと。
世の中のために能力を活かすことを考えること。
これらを心の隅に留めて、私自身これからの人生の選択を行いたいと思いました。
正に「先達あらまほしきこと」だなと実感させていただいたご講演でした。
中村様、この度は大変ありがとうございました。
仲川久礼亜(総合文化研究科 博士課程)

藤掛 直人
株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース 事業戦略マーケティング部 部長
1991年生まれ、大阪府出身。2014年東京大学経済学部卒業、同年株式会社ディー・エヌ・エーに⼊社。スマホゲームのプロデューサーを歴任後、2017年よりスポーツ領域の新規事業開発を担当し、子会社立ち上げ・PMI・経営戦略立案を主導。体制構築後はマーケティング領域を統括し、観客動員数リーグ1位や、YouTubeチャンネル登録者数 JリーグとBリーグ含め1位などの成果を収める。著書に『ファンをつくる力 デジタルで仕組み化できる、2年で25倍増の顧客分析マーケティング』(日経BP、2022年)。
今回は株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース事業戦略マーケティング部 部長の藤掛 直人様にご講演いただきました。
藤掛さんはまずご自身のお仕事であるスポーツビジネスについて、どのように立ち上げ、またどのように拡大していったのかを詳しくお話しくださいました。周囲の物事や現象をよく観察し、そこに潜むチャンスと課題に気づくことの大切さが強く感じられました。なた、学生時代の部活や趣味と、今のお仕事内容との関連のお話も大変興味深く、今部活で活躍している学生にとっては特に刺激的だったのではないかと思います。
ご自身の経験から「無駄な経験などはない」、他人の基準や他人の評価などの「他人軸」を気にせず、焦らずに勇気を出して、「自分のやりたいことは何か」をきちんと考え、「自分軸」を作ることが大切ということもお話しくださいました。さらに、「今やりたいことが決まっていなくても大丈夫、興味のあることにチャレンジすることで、少しずつ進路が明確になっていくということも語られました。
今大学生である私たちは、急速に変化している社会への不安や、これからの進路の選択への躊躇など、人生に対する迷いがたくさんあります。未来に対して、自分のやりたいことを明確にできなかったり、間違いや失敗を恐れたり、他人の目線を気にしすぎてしまったりすることがあります。藤掛さんのお話から学生は勇気をもらったのではないかと思います。
この度はご講演いただき、誠にありがとうございました。
楼 悦(総合文化研究科修士課程)

古川 千絵
Simon Fraser University(カナダ)専任講師(Department of World languages and literatures)
東京都出身。98年東京大学文科二類入学、文学部行動文化学科(社会学専修)卒業。大学院では教育社会学専攻。博士課程進学後の2005年、米国イリノイ大学(Educational policy studies)に移籍。在学中は結婚、夫の転職に伴うシアトル、セントルイスへの転居、親の癌闘病、不妊治療と出産等で研究が何度も中断するも2016年博士号取得。大学院から非常勤等で続けていた日本語教師の経験を生かし、2018年サイモンフレーザー大学で日本語講師となる。三児の母。7年前から続く長女の場面緘黙症との向き合い方、家族関係が自分の中の大きなテーマとなっており、今後の研究課題としても考えている。
今回はカナダのサイモンフレーザー大学で日本語講師として勤務されている古川千絵先生にご講演いただきました。
古川先生はまず東大での学生時代の思い出を振り返り、ゼミでの初めての発表や、大学院入試のご経験などについて語ってくださいました。さらに、その後進学されたアメリカの大学院での研究と仕事、子育てのお話を具体的にしてくださり、人生のさまざまな局面で起こる想定外の出来事とそのなかでどのように過ごしてきたのかをざっくばらんに教えて下さいました。また、ご自身の海外留学のご経験から「語学はちゃんとできればできるほど世界もできることも広がるので(学生時代に)やっておくに越したことはない」とおっしゃいました。
穏やかな語り口のなかにも、やりたいことを最後まで貫いてやり遂げる先生の強さや、さまざまな困難にあっても、大事なことを忘れずに乗り越えられてきたしなやかさのようなものを感じました。
最後に、古川先生が大事にしているという言葉をご紹介くださいました。周りの人がどんな経験をして、どんな思いでいるかということはなかなかわからないけれども、想像力をもって優しく接することを忘れないようにという意味の言葉(英語で”You never know what someone Is going through, so be kind.”)でした。古川先生から学生へのメッセージとして、忘れたくない言葉になりました。
この度はご講演いただき、誠にありがとうございました。
楼 悦(総合文化研究科修士課程)

ファイスト ワレーリヤ(Valeriya Fajst)
Strategy planning & data analysis at Rakuten Mobile, Inc.
Born and raised in Russia, Novosibirsk, has lived in Japan since 2014. I did my bachelor’s and master’s degree in linguistics at UTokyo, graduating in 2021. After graduation I joined Rakuten Group as a new grad, and after 6 months of training got assigned to Transmission Network Strategy Planning division at Rakuten Mobile, Inc. My day-to-day job mainly consists of data analysis, and although I had very little prior experience in it I came to like it and am planning to advance my career in this field.
本日のキャリア教室では、2021年に東京大学にて社会言語学を専攻され、修士課程を卒業後、楽天グループに入社、現在は楽天モバイルにてネットワーク伝達に関する企業戦略とデータ解析に携わっている、ファイストワレーリヤ (Valeriya Fajst)様にご講演いただきました。
今回の講演では、主にご自身のこれまでのキャリアについて、日本への留学の経緯や自身の学生生活を交えながら語ってくださいました。
ワレーリヤさんはロシアの国内情勢に危機感を覚え、国外に出たいという強い思いを高校生の頃から持っていたそうです。また、日本のアニメなどが大好だったことから、日本語を学び、日本への留学をするようになったとのことでした。
2010年、モスクワの大会で日本語によるスピーチを披露して見事優勝し、2011年の夏、初めて日本への渡航の切符をつかみました。その数年後、様々な試験や面接を突破して、見事に東京大学への留学を果たしました。
今回の講演の中で、ワレーリヤさんのボランティア活動への情熱が強く印象に残りました。様々な観点からドキュメンタリー映画を見ては、SNSを利用してボランティア活動へ参加していたそうです。大学内でも食堂のメニューにヴィーガンを取り入れるなど、積極的に行動を起こしていました。自分で行動を起こす大切さを学ぶことができました。
この度は素晴らしい講演をありがとうございました。
伊藤竜星(総合文化研究科 修士課程)

堀井 有紀
家庭裁判所調査官
福井県出身。2004年3月東京大学文学部行動文化学科心理専修課程卒業。同年4月東京家庭裁判所採用。その後、静岡家庭裁判所沼津支部、神戸家庭裁判所、大阪家庭裁判所等、各地の家庭裁判所で勤務。非行をした少年や離婚等の家庭の問題で家庭裁判所に係属した当事者等について調査を行う家庭裁判所調査官として働く。3児の母であり、仕事と子育ての両立を目指す。公認心理師。
第3回となる今回は、家庭裁判所調査官である堀井有紀さんにご講演いただきました。堀井さんは本学文学部行動文化学科心理専修課程を卒業後、各地の家庭裁判所で勤務されています。心理職公務員としてのキャリアを積まれると同時に、3児の母親でもあり、講義では学生時代の話や調査官の業務についてだけでなく、仕事と子育ての両立についてもお話しいただきました。
家庭裁判所調査官の業務についてご説明された後、進学・進路選択についてご自身の体験をお話しされました。心理職公務員という道を選ぶにあたって、当時何を思っていたのかを披瀝する姿はどこか学生に寄り添うようでした。
その後は、仕事と子育てについて話されました。私が最も印象的だったのは、お子さんが病気にかかった時の日記を提示しながら、その体験を話されている姿です。その身振り、言葉からはやはり臨場感が伝わってきました。また、男女問わず自分ができる範囲で当事者意識として家庭にかかわることの大切さを強調する姿は非常に印象的でした。仕事も家庭も大切にされる堀井さんが、”等身大の女性”として自身の体験を話されることで、勇気づけられる学生が多くいたようです。
この講義は、多くの学生にとって、より広い視点から人生を考える契機になったように思います。スーパーウーマンだけではなく、”普通の人”が仕事と育児の両立を実現できる社会になってほしいという堀井さんの願いは、これから、ゆるやかに拡がりだしていくことになるのでしょう。
松本岳 (東京大学大学院 総合文化研究科 修士課程)

成田 明光
沖縄科学技術大学大学院 有機・炭素ナノ材料ユニット 准教授
2008年東京大学理学部化学科卒業。2010年、同大学院理学系研究科化学専攻修士課程修了後に渡独し、マックス・プランク高分子研究所にて有機化学の手法を利用したナノカーボン材料の合成研究に取り組む。欧州委員会による複数の多国間プロジェクトにも携わりつつ2014年に博士号を取得し、その後同研究所でプロジェクトリーダーとして研究を続ける。2018年より沖縄科学技術大学院大学での研究室立ち上げ準備を進め、2020年に帰国、現在に至る。
本日は沖縄科学技術大学院大学(OIST)にて有機・炭素ナノ材料ユニットを統轄されている准教授の成田明光先生にご講演いただきました。ご専門は、有機化学の手法を利用したナノカーボン材料の合成研究です。
成田先生は2010年、東京大学大学院理学系研究科化学専攻修士課程修了の後に渡独し、マックス・プランク高分子研究所にて博士号の学位を取得されました。学部生の頃より語学に興味がありドイツ語やフランス語を自主的に学んでいたことや、日本での学位取得に比べてより良い経済状況が望めることから、海外での博士号取得に踏み切られたそうです。
博士号取得の後も、多国間プロジェクトに多く携わりつつ同研究所でプロジェクトリーダーとして研究を続けられていました。そして2018年より、ドイツでの研究の傍らでOISTでの研究室立ち上げ準備を進め、2020年に帰国、現在は准教授としてユニットを統轄されています。
ご講演の中では、マックス・プランク研究所やOISTの概要・特長についてお話しいただき、これから大学院進学を将来の選択肢の1つとして検討するであろう多くの学生にとって、大変有意義なお話であったと思います。
また、実際に成田先生が今までに携わられた欧州委員会の多国間プロジェクトについてもご説明いただき、とても印象的でした。世界を舞台に活躍されている研究者の実態を目の当たりにし、私自身、国境を超えて世界を牽引する研究者像への憧れを覚えました。
学生も、普段あまり触れる機会のない研究分野や研究生活のお話に大変興味を惹かれている様子でした。研究に関してだけでなく、海外や沖縄での経験など、さまざまな新たな可能性を提示するご講演であったように思います。
成田先生、この度は貴重なお話をお聞かせいただきまして、誠にありがとうございました。
仲川久礼亜(総合文化研究科 博士課程)

𠮷田 覚
元日本データパシフィック(株) 代表取締役社長
1948年 京都府生まれ。1972年京都大学農学部卒業。 13年間の総合商社勤務(安宅産業、伊藤忠商事)。その間、1980年から5年間、機械担当マネージャとしてシドニー駐在。 1985年、総合商社を退社して日本データパシフィック(株)設立。代表取締役に就任。e-Learningシステム、e-Learning教材を開発し、大学等の教育機関に販売。 2021年、日本データパシフィック(株)での役職を退任し、北海道 音威子府村で寒冷地におけるお茶の木の栽培に挑戦中。
本日のキャリア教室では、元日本データパシフィック株式会社代表取締役社長、吉田覚さんにご講演いただきました。吉田さんはこれまでの登壇者の方々の中で最年長の講師で、豊富なキャリア経験を話してくださいました。
吉田さんは、1972年に京都大学農学部林産工学科をご卒業され、総合商社の安宅産業に入社し国内部門の住宅事業部門の担当に就きました。その後、貿易部門の農業機械輸出入部門の単体機械の担当に異動しましたが、1977年の安宅産業との合併により、1980年から伊藤忠商事に勤務することになりました。5年ほどシドニー支店に駐在していたそうです。
1985年に伊藤忠商事を退社し、同年、ご自身で「日本データパシフィック株式会社」を起業しました。起業当初はパソコンのないパソコン関連会社で、初年度は給料も出せないほど赤字続きで大変な苦労をしたそうです。ですが、オーストラリアの会社の日本進出や、日本の会社のオーストラリア進出の手助けをする形でコンサルティングを受け持ちながら、その陰でパソコン市場を拡大させていき、1986年にオーストラリア大使館の紹介を受けてTypequick社の日本代表となってから、現在でも続く教育ソフトウェアやe-Learningシステムの自社開発、そしてe-Learning教材を開発・販売する企業にまで成長しました。現在の取引会社の中には、あのSoftbankもあるそうです。
今回のご講演では事業経営の難しさを、会社の起業に際しての心構えから、資金面・他社との競合・事業の継続・顧客からのクレームやトラブルの対応に至るまで、多方面にわたって丁寧に教えてくださいました。会社の起業という冒険心のみならず、多くの困難に直面しても諦めずに解決策を模索し続けた吉田さんの姿勢、そして企業経営に対する吉田さんの熱意を、分野は違いますが私も見習わなければならないと思いました。就職活動における企業の面接官側の意見まで聞けたので、本当に貴重な講演になりました。
この度はご講演いただき、大変ありがとうございました。
伊藤竜星(総合文化研究科 修士課程)
キャリア・ワークショップ
(実施:キャリアサポート室)
今回の授業では、本学キャリアサポート室のスタッフの方々にお越しいただき、学生自身が自分のキャリアを考えるためのワークショップを行いました。このワークショップの目的は、変化の激しい時代を生きていくために大切なことを理解し、今後の学生生活やキャリアを考えるきっかけにすることと、そのために重要な自分らしさとは何かを知ることです。
ますます不確実となる未来の中で、自分らしさを起点に新たな答えを創りだしていくことが重要であると考えられます。この「自分らしさ」とは、能力や動機、意味・価値に直結するものであり、これらの「自分らしさ」が今後のキャリアの創造に繋がっていくものであることは言うまでもありません。
最初に「自分らしさ」をみつけるためのワークを行いました。具体的には、これまでの人生を振り返るために、ライフラインチャートを作成し、これまでの人生における出来事について自分に問いかけました。そして、グラフに表れる自分の特徴を探りました。多くの学生にとって、人間関係や学業がその時代における”気持ち”の物差しになっているようでした。また、コロナ禍によって気持ちが沈んだという学生はやはり多かったようです。
次に、今後に向けて、磨きたいものを考えました。「社会人基礎力」(社会において多様な人々と共働するために必要な基礎的な力)のうち、自分が得意だと思う力や強化すべき力についてグループワークを通じて考えました。他人と話すことを通じて、新たな「自分らしさ」に気づく学生もいたようです。講師の方からは、社会人基礎力は、先天的に備わるものではなく、経験を通じて身に付くものであり、学生生活を通じて伸ばすことができるとの説明がありました。
授業の最後には、講師の方から、変化の激しい時代にはチャンスを自ら掴みに行く姿勢が大切だというお話がありました。自分のよりどころ、すなわち「自分らしさ」を探索し、それを明らかにするために、活動の目的や自分にとっての意味を考えるということです。
今回のワークショップに参加した一人ひとりが、多様な個性を持つことは何よりも明らかであり、また、それぞれの未来が言葉に到底尽くせぬほど複雑多岐にわたるものであることは容易に想像がつきます。彼らが、予測しがたい未来を主体的・積極的に生き、キャリア・人生を豊かにしていくためのヒントが、この授業にはたくさん込められていたと私は強く感じています。
松本 岳(東京大学大学院総合文化研究科 修士課程)
ふりかえり
実施:キャリア教室担当教員
キャリア教室最終回では、これまでにゲストとしてお越しいただいた方々のお話の内容をふりかえるワークショップを行いました。
まず、各回の記録を読みながら、ゲストがお話くださった内容と、その時に自分自身が感じたことや考えたことをそれぞれ思い出し、他の学生と共有しました。その上で、学生が自らの今後の「歩み」について考え、行動するきっかけにできればということで、同世代である学生同士で話したいテーマを考えました。一人ひとりが考え出した数多くのテーマの中からクラス全体で複数選び出し、5人程度のグループに分かれて意見交換を行いました。
選ばれたテーマは、キャリア選択をしていく上で何を基準にしていくか、自分の「幸せ」の定義、留学、東大にいる意味などです。
仕事を選ぶ際、やりたいことを優先すべきか、待遇や条件を優先すべきかということについて考えを述べあうグループ、自分自身にとっての「幸せ」がまだわからないので、将来何か問題が生じたときに自分がぶれてしまうのではないかと不安を共有し、今思う「幸せ」について考えるグループ、今大学で行っている学びが将来にどのように結びついているのかわからないという問題意識から、今学期習得した知識と思考力などの力についてふりかえって考えるグループなど・・・、テーマに沿いながらも自由に思考を巡らせ、自分自身の「将来」と「今」をつなげようとしていました。他の学生の意見に耳を傾けて、自分とは違う考え方に触れたことも大きな刺激になっていたようです。今後さらに思考と経験を重ね、自分の道を切り拓いていってくれることを担当教員一同、願っています。
髙橋 史子(東京大学教養学部附属教養教育高度化機構社会連携部門・特任講師)
| 第1回 10月7日(金) | ガイダンス(オンライン) |
|---|---|
| 第2回 10月14日(金) | 佐野 悠樹 |
| 10月21日(金) | 休講(1月18日(水)に補講) |
| 第3回 10月28日(金) | 堀井 有紀(ゲストはオンライン参加) |
| 第4回 11月4日(金) | ファイスト ワレーリヤ |
| 第5回 11月11日(金) | 高祖 歩美 |
| 第6回 11月25日(金) | 中村 有沙 |
| 第7回 12月2日(金) | 藤掛 直人 |
| 第8回 12月9日(金) | キャリア・ワークショップ |
| 第9回 12月16日(金) | 𠮷田 覚 |
| 第10回 12月23日(金) | 小見 和也 |
| 第11回 1月6日(金) | 成田 明光 |
| 【補講】第12回 1月18日(水) | 古川 千絵(ゲストはオンライン参加) |
| 第13回 1月20日(金) | 振り返り |
info.sr.komex-group[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp
東京大学教養教育高度化機構 社会連携部門([at]を@に書き換えてください)